
風立ちぬ [DVD]
2013年に公開された宮崎駿監督の映画「風立ちぬ」は、堀越二郎という実在の人物をもとにしているが、実在の人物とは違うものにしている。
どう違うか?
宮崎駿監督は何を考えてそうしたか?(敬称略)

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
夢

少年の夢
映画「風立ちぬ」
映画「風立ちぬ」は、主人公の少年が夢で飛行機に乗って空を飛んでいくところから始まる。

風立ちぬ [Blu-ray]
「零戦 その誕生と栄光の記録」
堀越二郎は著書「零戦 その誕生と栄光の記録」で次のように語っている。
自分が作った軽い小さい飛行機に乗り、野こえ、山こえ、低空飛行を楽しんでいる夢をよく見たものである。
「 零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、角川文庫、20頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
考察
映画「風立ちぬ」のはじめに少年の時の夢が描かれているのは、「零戦 その誕生と栄光の記録」の記述をもとにしているようである。
違うと思われるところもある。
堀越二郎は「零戦 その誕生と栄光の記録」において、少年時代の「飛行機への関心は、中学から高校に進むにつれ、いつしか私の心の表面からは消えていった」と言い、「大学進学にあたってコースを決めなければならなくなったとき、少年時代の記憶が心の底からよみがえってきた」と語っている。(「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、21頁)
映画「風立ちぬ」の堀越二郎は、少年時代から飛行機を設計するという夢を持っていて、その夢に向かって進んだ結果、大人になって飛行機を設計する仕事に就いたように見える。
ここに両者の違いが現れている。
夢は自分の内にあるものである。
映画「風立ちぬ」の堀越二郎は、少年の時からひたすら自分の内にある夢に向かって進んでいる。そして、そのことによって外からも、社会的にも認められることになっている。
「零戦 その誕生と栄光の記録」の堀越二郎は、少年時代の夢から出発しているのではなく、「大学進学にあたってコースを決めなければならなくなった」という外との関係から出発している。
技術者と芸術家
芸術家
映画「風立ちぬ」の中で主人公が繰り返し見る夢において、主人公の目的は美であることが明らかにされている。
夢に出て来るメフィストフェレス役のカプローニは「飛行機は戦争の道具でも、商売の手立てでもない。飛行機は美しい夢だ。設計家は夢に形を与えるのだ」という。
目的は美であって、「戦争の道具」でも「商売の手立て」でもないというのである。
技術者
現実の堀越二郎も、飛行機の美しさにも気を遣っていた。
零戦に対して「美しい」とも叫んだ。
私は一瞬、自分がこの飛行機の設計者であることも忘れて、
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫) 」、110頁
「美しい!」
と、咽喉の底で叫んでいた。

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
しかしこれは自分が飛行機の設計者であることを忘れた一瞬のことであった。
「零戦 その誕生と栄光の記録」で堀越二郎は美以外の様々なことについて考えていたことを明らかにしている。
堀越二郎は技術者と芸術家とを区別して、自分は技術者だとしている。
技術者の仕事というものは、芸術家の自由奔放な空想とはちがって、いつもきびしい現実的な条件や要請がつきまとう。しかし、その枠の中で水準の高い仕事をなしとげるためには、徹底した合理精神とともに、既成の考え方を打ち破ってゆくだけの自由な発想が必要なこともまた事実である。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、226頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
技術者も、高い水準の仕事のためには、芸術家と同じように自由な発想が求められるが、芸術家と違って、いつも「きびしい現実的な条件や要請」という「枠の中で」仕事しなくてはならないというのである。
堀越二郎自ら、自分は宮崎駿の語るような芸術家ではないと語っていたのである。
「零戦」はまさにそういう技術者の仕事として作られたという。
思えば零戦ほど、与えられた条件と、その条件から考えられるぎりぎりの成果の上に一歩をふみ出すための努力が、象徴的にあらわれているものはめったにないような気がする。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、226頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
堀越二郎はそう言う意味で「戦争の道具」として飛行機を作っていたのである。
条件との関係
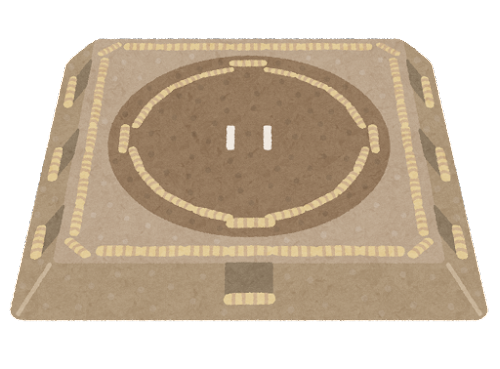
宮崎駿は堀越二郎の言葉を受けて、次のように語っている。
いろんな意見が出てきて、それをすり合わせるのが大変だったって書いてあるけど、何を作るかっていうのは、はじめから彼の中に強烈にあったんだと思います。それに軍隊の要求を近寄せただけでね。
「Cut」2013年9月号、20頁
宮崎駿はこのように堀越二郎は軍隊の要求から超然とした理想を自分の内にもっていた人物とみなしている。
これは堀越二郎が「零戦 その誕生と栄光の記録」において「きびしい現実的な条件や要請」という「枠の中で水準の高い仕事をなしとげる」ということと相容れない。
堀越二郎の仕事は条件を前提としたものである。海軍の発注、外国との競争、日本の資源等という条件を前提としたものである。
零戦ができるまで
零戦ができるまでの堀越二郎の創造と与えられた条件との関係について大雑把にまとめる。
堀越二郎は三菱内燃機株式会社(後の三菱重工業)の一員として、陸海軍の注文を受けて、戦闘機を設計していた。
陸軍や海軍の第一線機については、何社かに競争試作させ、勝ったほうの試作機が、軍に採用されて量産の注文を受けるという習慣ができたばかりの時代であった。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、27頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
ワシントン、ロンドンの軍縮会議で軍艦の保有率が大幅に制限された状況で、航空兵力に目が向けられた。
そしてその技術について外国への依存を断ち切る政策として昭和6~7年に海軍によって「航空技術自立計画」が立案された。航空技術の研究機関の総合機関として「海軍航空廠」が設立された。
七試
昭和7年にその計画の第一弾「七試(昭和七年試作発令)」の五機種が発注された。
堀越二郎はそのうちの一つ七試艦上戦闘機の設計主任を命ぜられた。
私がはじめて設計主任を命じられたのは、このうちの一つである七試艦上戦闘機だったのである。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、28頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
結局この時にはうまくいかなかった。
九試
昭和九年に海軍は「九試」を発注した。
堀越二郎はまた設計主任となった。
この時には海軍が要求をゆるめていて「われわれの自由な創造意欲をかきたててくれるものがあった」と堀越二郎は語っている。
また「まがりなりにも、七試という新しい戦闘機のはじめから終わりまでを体験し、設計チームのメンバーにも息がかよいあうようになっていた」と語っている。(「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」 、34頁)
堀越二郎の設計した九試単戦は、「速度で世界のトップをいきながら、格闘戦のチャンピオンでもあるという、世界の常識を破った」ものとなった。
そして昭和十一年秋に、「九六式一号艦上戦闘機」として正式に採用された。(「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、41頁)
十二試
昭和十二年十月に「十二試」の艦上戦闘機の計画要求書が交付された。
「この要求書は、当時の航空界の常識では、とても考えられないことを要求していた」と堀越二郎は言う。( 「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、10頁)
当時の戦闘機がふつうもっていた航続力を大幅に二倍程度にまで伸ばし、しかも当時、空戦性能においては、世界にその右に出るもののなかった九六艦上戦闘機、略して九六艦戦の二号一型よりすぐれた空戦性能をもたなくてはならない。速度も、九六艦戦の最大速度四百五十キロを大幅に抜く五百キロを要求していた。これは当時活躍していたどの戦闘機にもまさるものであった。さらにその九六艦戦では七・七ミリ機銃二挺しかなかったものを、それより格段に重装備で、七・七ミリ機銃とはちがい、爆薬をしこんだ炸裂弾を発射する二十ミリ機銃を、二挺加えよといっている。(中略)一人乗りの戦闘機にこれを装備するのは、世界でもはじめてのことであった。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、13頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
堀越二郎は昭和十三年一月の官民合同の研究会で、要求の一部を引き下げることをもとめた。
しかし海軍側からは「引き下げられない」と言われた。(「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、51~53頁)
そこで堀越二郎は様々な問題について考えて、その要求にかなうような戦闘機を設計した。
昭和十五年七月末、十二試艦戦は制式機として採用され、日本紀元二六〇〇年の末尾の零をとって「零式艦上戦闘機・一一型」と名付けられた。「零戦」とはその略称である。
まとめ
このように「七試」でも「九試」でも「十二試」でも、堀越二郎の仕事は、海軍の発注に対して、艦上戦闘機を設計することにあった。
海軍との関係
映画「風立ちぬ」では、「注文主」の海軍の軍人の言うことを会議で堀越二郎が聞くところで、前に並んだ海軍の軍人複数が意味のないことをうるさく言っているような演出になっている。
そのことについて宮崎駿は次のように語っている。
軍人が偉そうなこと言ったってろくでもない奴らだから、ほんとに大局観も何もない、国を誤らせた連中に弁解させたり、しゃべらせたりする必要はない。だからああいうふうに描こうって、初めから決めてました。
「Cut」2013年9月号、19頁
宮崎駿は、国を誤らせた軍人の言葉を聞く必要がないと考えているようである。
しかしすべての軍人が「国を誤らせた」のではない。
特に堀越二郎は、海軍の注文を受けて海軍のために戦闘機を作るという条件があったからこそ零戦はできたと語っているように、零戦は海軍によってできたということもできる。
堀越二郎も「指導層の思慮と責任感の不足にもとづく政治の貧困」を問題としている。(「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、224頁)
しかしそのことと、海軍が戦闘機を発注したこととは別のことである。
「零戦 その誕生と栄光の記録」で零戦について堀越二郎が海軍とやりとりしているところをとりあげてみよう。
計画要求書
まず昭和十二年十月六日に堀越二郎が受け取った計画要求書は、無理と思われるほどのものであった。
そこで堀越二郎はその要求書がつくられた会議の様子を想像している。
私には、この要求書がつくられた会議の雰囲気が、目に見えるようだった。要求する側の人間ばかりが集まって、あれもこれもと盛りこんでしまったのだ。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、15頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
しかし堀越二郎は相手を馬鹿にしていない。
「その人たちは、それぞれの部門のベテランで、日本をとりまく世界の情勢を考えてのことにちがいない」と言い、「私は、この計画要求書に、日本の国のせっぱつまった要請を聞く思いがした」と言っている。(「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、15、16頁)
堀越二郎はその計画要求書に、日本を取り巻く世界の情勢に対する日本の要請を聞き取っていたのである。
堀越二郎は、発注した海軍に同情している。
零戦が出来たのも、そういう計画要求書があったからだと堀越二郎は考えている。
官民合同の研究会
昭和十三年一月十七日の研究会で堀越二郎は海軍側に要求の一部を引き下げることを求めたが、海軍は「引き下げられない」と言った。
そこでも堀越二郎は海軍側を馬鹿にしていない。「この困難な要求に決意を新たにして立ち向かわねばならないことをひしひしと感じていた」と書いている。(「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、53頁)
審議会
昭和十三年四月十三日に海軍航空廠で審議会が開かれた。
そこで格闘力を優先させるべきだという源田少佐と、速度、航続力を優先させるべきだという柴田少佐とが対立した。
そのことについて堀越二郎は次のように語っている。
この二人の意見は、だれが見てもそれぞれ正しいことを言っているのであり、それゆえに議論へ永久に平行線をたどるだろう。この交わることのない議論にピリオドを打つには、設計者が現実に要求どおりの物を作ってみせる以外にはない。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、80頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
ここでも海軍側を馬鹿にしているのではない。
海軍部内の動揺
華中の第一線にある第十二航空隊から、堀越二郎の構想に対して反対が唱えられたことがあった。
それに対して堀越二郎が航空本部の巖谷少佐に自分の見解を伝えると、「巖谷少佐はかなり同意してくれた」という。(「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、87頁)
このように海軍が堀越二郎の見解に同意したからこそ零戦はできたのである。
まとめ
宮崎駿は次のように語っている。
会議ではものが決まらないようにしようって、この映画を作る時に思ったんです。
「Cut」2013年9月号、19頁
しかし宮崎駿も「『零戦』っていう本も会議だらけですよ。誰がどんなことを言った、誰がどんなことを言ったとかね」と言っている。(「Cut」2013年9月号、19頁)
「零戦 その誕生と栄光の記録」には多くの会議のことが書かれている。零戦は、多くの会議で様々な要求を受けた上で出来たのである。
宮崎駿はそのことを知っていたのに、映画では「会議ではものが決まらないようにし」た。
このように宮崎駿は映画「風立ちぬ」で、事実とは異なることをわざと描いているのである。
外国との関係
堀越二郎が設計していた戦闘機は、外国の軍隊と戦うためのものである。
それゆえに堀越二郎は外国のことをいつも意識していた。
映画「風立ちぬ」でも主人公が外国を意識するところが描かれている。
しかし外国に対する考えが違うように見える。
「零戦 その誕生と栄光の記録」で堀越二郎は、いかにして零戦によって日本の技術で欧米に対して先に進むことができたかを語っているのに、 映画「風立ちぬ」の堀越二郎は、外国に圧倒されているように見える。
ドイツ
たとえば堀越二郎がドイツに視察に行ったところ。
映画では、堀越二郎は欧米の重みにつぶされそうに見える。
「零戦 その誕生と栄光の記録」では、堀越二郎は次のように語っている。
会社から派遣されて、ドイツとアメリカの飛行機工場にはいって、工場を視察し、設計者と討論をしたり、ドイツ、イギリス、フランス、アメリカの工場見学、各国の航空技術に関する刊行物の調査などにも手をつけていた。それらの経験から、日本でも適当な方針と組織、規模があれば、小型機で彼らに追いつくことは、一足飛びには不可能だが、そう長い年月はかかるまいという考え方をしていた。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、28頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
このように堀越二郎は、日本が技術においても資源においても、欧米の先進国の後を追ってきたことを認めていると同時に、間もなく追いつくことができるとも考えていた。
「九試」
堀越二郎は「九試」をきっかけとして、日本の飛行機設計は欧米先進国に対抗することができるようになったと考えていた。
この九六艦戦誕生をきっかけとして、日本の飛行機設計者のあいだに、自分の頭で考え、自分の足で歩くときがきたという自覚が広がった。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、41頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
悲恋

映画「風立ちぬ」では、主人公の堀越二郎は里見菜穂子と出会って結婚することになっている。
「零戦 その誕生と栄光の記録」には全く書かれていないことである。
堀越二郎の話に堀辰雄の話を入れたと宮崎駿は語っている。
映画「風立ちぬ」で何故に堀越二郎と里見菜穂子の恋愛がさしこまれたのか?
美
映画「風立ちぬ」において、堀越二郎は超然としてひたすら美を追い求める人として描かれている。
この映画の里見菜穂子は、そのように美を追い求める人の前に現れた美の一つである。
美を追い求めて戦闘機を設計し、美を追い求めて美女と結婚するのである。
しあわせ
いずれの場合も、追い求めた目標が苦も無く手に入ってしまう。―映画「風立ちぬ」の主人公は、恵まれた、しあわせな人である。
暗黒面
ところで映画「風立ちぬ」は、そのように美を追い求める主人公が、そのことの暗黒面をも見るという話になっている。
貧乏な子供を見て、恵まれた自分との違いについて考えるとか。
里見菜穂子に関しても、その暗黒面が描かれる。―里見菜穂子を置いて飛行機設計に没頭するとか、里見菜穂子がいるのに煙草を吸うとか、里見菜穂子が悲しいことになってしまうとか。
現実
映画「風立ちぬ」で堀越二郎と里見菜穂子の恋愛がさしこまれたもう一つの理由として、堀越二郎が「零戦 その誕生と栄光の記録」で語ったような、零戦ができるまでの苦労を描かないようにするという意図があったのではないか?
「零戦 その誕生と栄光の記録」では、堀越二郎は昭和十二年十月の海軍の計画要求書を受け取ってから零戦を作るまで、与えられた大変な問題を解決するために、全身全霊をかけていたように見える。
会社にいるときは、ややもすると目先の仕事だけに追われてしまうことが多かった。だから、私のこの頭の中での作業は、通勤の満員電車の中でも、家に帰ってからも、続くことがあった。夜中に目がさめてしまい、暗闇を見つめながら考えたこともあったし、夜おそく床にはいっても、なかなか寝つけないこともあった。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、56頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
こういうところを見ると、映画の堀越二郎のように軽井沢で遊んでいる暇はなかったのではないかと思ってしまう。
その多忙の中で、私たちは昭和十三年の四月を迎えた。が、桜の花の咲くのも散るのも、気にとめている余裕などあろうはずがなかった。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、76頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
そして昭和十四年。
昭和十四年の正月が開けた。それは、私がこの半年のあいだに味わった、もっとも平和なひとときであった。一昨年の六月に生まれた長男とも、このところ仕事に追われて、ろくに顔を合わせるひますらなかった。やっといま、親子そろった家庭らしい生活が、ちょっとの間でも復活したのだ。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、90頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
昭和十四年の正月にはじめて「親子そろった家庭らしい生活が、ちょっとの間でも復活した」のである。
それまでそういうことはできなかった。この時にも「ちょっとの間」しかできなかった。
現実の堀越二郎がそれだけ苦労していた時に、映画「風立ちぬ」はそのことを描かず、堀越二郎は美女とメロドラマを演じていたことにしているのである。
現実の堀越二郎の苦労の話を描きたくないという意図がなかったとは思えない。
美女との恋物語が描かれる分だけ、零戦を生み出す話を描く時間はなくなる。恋物語が差し込まれることによって、関心は分散させられる。恋物語をしていられるほど余裕があった印象が与えられる。
「零戦 その誕生と栄光の記録」は、堀越二郎が難解な問題を苦労して解決していくところを描いた記録である。
映画「風立ちぬ」では、堀越二郎は特に苦労もせずに問題を解決してしまう。
堀越二郎を描くこと

宮崎駿は、映画「風立ちぬ」によって堀越二郎を「取り戻した」と語っている。
『風立ちぬ』で、僕は僕の堀越二郎を取り戻したんだと思ってるんです、60年かかって。
「Cut」2013年9月号、15頁
宮崎駿はそのことが映画「風立ちぬ」の目的であったという。
僕は自分のことを描いたんじゃない、堀越二郎を描いたんだ。二郎を取り戻したんです。僕流に取り戻したんです。
「Cut」2013年9月号、27頁
宮崎駿は何から堀越二郎を「取り戻した」のか?
「零戦神話」からである。
宮崎駿は次のように語る。
「コンプレックスの塊だった連中の一部が、『零戦はすごかったんだ』っていう話をしはじめた」が「ほとんどが嘘の塊」であったと言い、「今、零戦の映画企画があるらしいですけど、それは嘘八百を書いた架空戦記をもとにして、零戦の物語を作ろうとしている」と言って、そういう「零戦神話」に対して、堀越二郎を「取り戻した」、と。(「Cut」2013年9月号、14~15頁)
ところで宮崎駿は、堀越二郎が自ら語るのと異なる堀越二郎を作っている。そのことはこれまで示してきた通りである。
宮崎駿は堀越二郎その人を「取り戻した」のではなくて、堀越二郎を別物にすることで「取り戻した」ことにしているのである。
堀越二郎は零戦について次のように語っている。
当時の世界の技術の潮流に乗ることだけに終始せず、世界の中の日本の国情をよく考えて、独特の考え方、哲学のもとに設計された「日本の血の通った飛行機」―それが零戦であった。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、4頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
そして「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」を書いた意図について次のように書いている。
これからの若い世代が、たんに技術界だけでなく、すべての分野で日本の将来をより立派に築いていくために、誇りと勇気と真心をもって努力されることを念願して、私はこの本を書いた。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、5頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
堀越二郎も零戦はすぐれたものだと語っている。堀越二郎が「零戦 その誕生と栄光の記録」を書いたのはそのためである。
それに対して宮崎駿は零戦はすごかったという話をやっつけたいと思っていた。そのために堀越二郎を現実とは違うものにしてしまった。
堀越二郎の遺族は 映画「風立ちぬ」を観て、いいと言ったと言う。
堀越二郎のご子息とその奥さんが、スタジオを見たいって、訪ねてきてくれたんですよね。
「Cut」2013年9月号、24頁
(中略)
『フィクションでございますんで』というお話はしたんですけども、観終わってね、ほんとに喜んでくれたんです。それで実にほっとしましたね。
そう言われてもやはり私はおさまらない。
堀越二郎に関する記事。
こまかいところ
その他に気になるところをいくつか取りあげる。
大学の講義
映画「風立ちぬ」で主人公が友人の本庄と大学の昼休みに食事に行った時に、堀越二郎がいつもサバをとることについて本庄が「マンネリズムだ。大学の講義と同じだ」というところ。
「零戦 その誕生と栄光の記録」で堀越二郎が語るところと違う。
航空に関する科学・技術は、その発祥地である欧米でもまだ歴史は浅く、体形づけられていなかった。だから、われわれの航空学科でも、講義の体系がなく、寄せ集めの感じだった。しかし、教室の雰囲気は、開拓時代にふさわしく、自由であり新鮮であり、所帯が小さいため、教官と学生のあいだも、学生同士もひじょうに親密だった。
「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、24頁

零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)
「開拓時代にふさわしく、自由であり新鮮であり」というのは、「マンネリズム」と反対である。
航空に関する科学・技術が欧米でもまだ歴史が浅かったということ、開拓時代であって講義の体系がなかったということは、歴史を論ずるときに重要なことではないか?
牛
三菱の名古屋の工場に牛がいて、戦闘機の試作機を岐阜の各務原飛行場まで牛車で運んでいくというところ。
堀越二郎は「零戦 その誕生と栄光の記録」でそのことについて説明している。
三菱の名古屋の工場は、岐阜県各務原飛行場から離れていた。
日本には平野が少なかったゆえに、飛行場は工場から離れたところにしかできなかったのである。
その離れた飛行場までの悪い道で飛行機に傷をつけないようにトラックではなく牛車で運んだのである。
堀越二郎はそのことについて「日本的な、うまい状況適応策であった」と言っている。(「零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫)」、100~101頁)
映画で本庄という人物がそのことについて「恐るべき後進性だよ」と言っているのは、堀越二郎の考えと違うのではないか。
宮崎駿はそういうところでも、堀越二郎の語ることに反して、日本の「後進性」を強調しているようである。

風立ちぬ [Blu-ray]




コメント